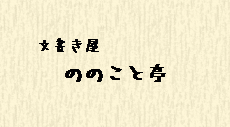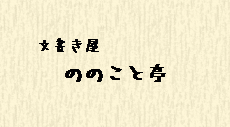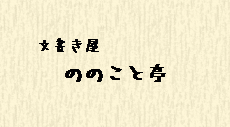 |
|
整地もままならない、畦道ともいえない道を歩く少女が二人。
半歩先を歩く少女は無表情で、それでも華美な面容は厳しくも無く、淡々と道を歩んでゆく。
先程交わした挨拶は単純で、互いの接点を寄せて見えることはできない。
しかし二人の距離は近いまま、行進曲さながらの歩幅で息を合わせている。
すると先んじた少女が、
「・・・雪下千華さん」
後行く少女に問いかける。
「ん、なに?」
千華、と呼ばれた少女、雪下千華は仕草を変えずに歩いた通りに返事をする。
「・・・昨日の現国、どう?」
言葉は短く、やもすると冷淡に感じる言葉は千華には馴染み深く、
「そうねー・・・まずまずかな」
事も無げに言って言葉を切り、
「そういう姫王子妃さんはどうだったのかしら?」
軽んじた語調で返す。
「・・・フルネームはやめて」
表情は変わることなく、それでも拒絶の言葉は否定感を緩ませて先を歩く少女、姫王子妃は、
「・・・そうね、・・・私もまぁまぁよ」
淡々と返す。
「そっか。・・・じゃ、来年も同じクラスになりそうね」
いつの間にか手に持った小さな手のひら大の書籍を開いていた千華は、
「そうかしら?」
珍しく間髪入れずに言葉を返す友人に捲る手を止める。
「・・・え?妃、理系じゃなかったっけ?」
「・・・・・・」
言葉はすぐに続かず、千華の自宅を過ぎてからの間見えなかった家姿が、少し先に見えてくる。
「・・・私・・・経済と歴史が良かったのよ」
小さく呟く。
「え!なに、妃文転するの?」
書籍をパタと閉じ、半歩先、すぐ前にいる妃を凝視する。
「・・・別に・・・そういう訳では無いけど」
区切った言葉はぶっきらぼうで、このままの会話を嫌うように下げていた視線を水平に上げる。
釣られて向けた視線の先、一軒の戸建てがもうすぐというところ。
オフホワイトの外壁に煉瓦色の屋根が鮮やかで、囲いの無い開けた様子は来る者を温かく迎え入れるようだ。
その玄関、比較的大きな一枚板の扉が開き、
「いってきまーす」
鈴を転がしたような爽やかな声音と共に、少女が現れる。
淡い茶色のダッフルコートは肩が滑って身丈にやや大きく、振り向いて揺れ開く裾からは墨を沈めたような深い黒色。
雪色の留め具で合わせた胸元からは濃い飴色のタイと鈍白色のシャツが覗く。
すぐに二人に気づいた少女は、
「あっ、おはよう二人ともー」
気さくに挨拶すると閉めかけていた扉を開いて顔を家内に突っ込み、
「おーにいちゃーん!千華ちゃんたち来てるよー」
可愛く声を張ると、玄関前の小さな階段を降りて二人に駆け寄る。
「おはよーゆいちゃん」
「・・・おはよう、唯理ちゃん」
元気よく現れた少女は双様の挨拶に笑顔を浮かべ、
「うん!今日も寒いねー」
淡い桃色の手袋に包まれた両手を顔の前で合わせ、吐息を吹きかける。
「また月理はご飯中?」
「うん、いつも通りだよー。あ、でも今日はパンだから更に遅いかも」
「え、パンなの?」
千華はややうんざりした顔つきで、
「月理、飲めないのにコーヒーつけるからなぁ」
「・・・そうね。しかもブラック」
小さく言葉を繋げる妃に、少女はやや困った顔をして、
「そうなの。お砂糖はいっぱい置いてあるんだけどねー」
千華は腕をめくり、翡翠色の皮ベルトに丸盤の時計を確認し、
「もう学校?まだ早くない?」
気を取り直したように少女は笑顔を浮かべ、
「うん、まだ学校じゃないよー。ちょっとお店で用があって」
ちらりと出てきた家の横、道に面した側は全てガラス張りの建物に目を向ける。
「・・・売り物の確認?」
「あ、うーんそうなのかな?・・・えっと、昨日気になるグッズをネットで見かけたから、それっぽいものうちにもなかったかなって」
「そっかー。じゃ私達も一緒しようかな。いいでしょ妃?」
「・・・えぇ。どうせしばらく待つものね」
嘆息を見せる妃。
「じゃあいこっか」
踏み出した少女に合わせて歩き出す。
と、
「笑乃さんはおうち?」
「ううん、お母さんは買い付けでもう出かけてるよー」
「そっか」
千華は少女の出てきた扉へと近づき、鍵のかかっていない扉をゆっくり開き、
「ふーじーみーやーくん!でーかーけーまーしょ!」
室内に向けて子供のような言葉を張り上げる。
そしてそのまま中へは入らず、扉を閉める手前、ガチャンと小さく食器の踊る音と共に、
「あっつ!」
呻くような叫び声が遠くに聞こえる。
千華は閉まった扉から手を離すと、ほくそ笑みながら、
「さっ、いこっか」
意気揚々と先陣を切って歩き出す。
少女はにこにこと笑顔を浮かべながら、
「これで早く出てくるかな?」
「・・・どうかしら。意地になってギリギリに出てくるかもね」
どうでもよいというように妃は表情を変えず、少女と並んで千華の後ろにつく。
ガラス張りの建物をなぞるように歩く三人。
戸建てのそれは平屋で、ガラスをサンドイッチしている外壁は樹齢を問いたくなるような燻された木造。
しかしてガラスも木目も丁寧に磨かれて艶光り、映りこむ少女達が輝きを放つ。
通りに平行だったガラス面はやがて湾曲し、足下はゆるやかなスロープになる。
すぐに終わりを告げる坂道は平らな面に変わり、煉瓦を敷き詰めた上には柔らかな起毛のマットが敷かれている。
立ち止まった二人の前に少女は歩き出て、内外を隔つ扉の前に立つ。
「わっ、可愛いこのマット。やっぱりいつも踏みにくいなぁ」
「うん、新しくしたんだー。テーマは夢うさぎだって」
淡い桃色と橙、円形の小さな何かをかき抱くうさぎは、何かを願うように目を瞑っている。
少女は扉の持ち手の上、手の平大の備え付けられた黒いボックスを下から引っ掛けるように開ける。
開いた中には小さなテンキーが並び、少女は事も無げに盤面を押し込んでいく。
そしてスカートの褶から鍵を取り出すと、素早く扉の鍵穴に差し込む。
カチャン。
乾いた音と共に扉が揺らぎ、少女が引くと難なく開いてゆく。
室内へ踏み出す少女と、後から続く少女達。
ふわりと香る室内。
外壁と同じ色合いの木目は掃き慣らされて外界からの光を反射し、店内に所狭しと並べ立てられた品々を明るく照らし出す。
迷いなく奥へと進む少女と、店内をきょろきょろ見回しながら進む少女達と。
「あれ!あんな子いたっけ?」
先ゆく少女は立ち止まって後ろを見やり、
「あ!うん。あの子は昨日お母さんが連れてきたのー」
「へぇー。珍しい置物?だね」
「優しそうなお顔でしょ?でね、あの子実はUSBメモリなの」
「へぇ、意外とハイカラね・・・でも根本折れちゃうんじゃないの?」
「へっへー。それはね」
少女は優しげな瞳を潤ませた白銀のうさぎの置物に近づき、
「・・・ほら!」
後ろからちょろりとコードを取り出す。
「あぁ、外付けみたいな感覚なのね」
近寄って、少女から受け取ると長さや位置をしげしげと観察する妃。
「?外付け?」
ハテナを浮かべた千華に、
「パソコンの記憶媒体のことよ。あなたの家にもあるじゃない」
「あぁ、あれかぁ・・・余り使わないからわからないよ」
千華も近づいて、重厚感のある白銀のうさぎにそっと触れる。
「・・・あれ?意外とぷにぷにしてる」
「そうなの!身体の丸い感じと合わせてマシュマロみたいでしょ?なんか特殊な素材を使ってるんだってー」
「あら、じゃあさぞお高いのでしょうね」
コードを置き、うさぎに触れる。
「・・・あらほんと。ぷにぷにしてるわ」
「それ私の手だから」
さわさわと触れるは千華の手。
「・・・あ、ほんと。よく触るとごわごわしてるわ」
「してないっ!ひどいよ妃ー」
触られていた手を引っ込め、もう片方の手でさする。
「うんうん。千華ちゃんの手は綺麗だよねー。すべぷにしてて、とっても素敵だよー」
「ほんと!?やったぁゆいちゃんに褒められちゃった」
にこにこ笑いながらうさぎの後頭部付近にあるボタンを押すと、しゅるりとまとまるしっぽのコード。
「そうね・・・手『は』綺麗かもね」
興味が削がれたように、もともと無かったかのように無表情で奥へと歩き始める妃。
「あわわ。手だけじゃなくてぜんぶ!ぜんぶ素敵だよ千華ちゃん」
「ううう、ゆいちゃん」
泣き真似をして少女に抱きつく千華。
「あの娘さんひどいと思いませんこと、唯理さん」
「あははは・・・」
歩きゆく妃をジト目で追う千華にごまかし笑いを浮かべる少女も、妃の後に続いて奥へと歩き出す。
歩きながら、
「そいえばあの子。お値段はどうするの?」
「うん、お母さんが『その時決めるわ』って」
「あはは、笑乃さんらしー」
「・・・それ」
いつの間にか立ち止まっていた妃は、
「・・・またおうちの子になるパターンよ、それ」
「妃、『それ』二回」
「・・・それくらいあり得るってことよ」
そうして三人集まったのは店の最奥。
「それで唯理ちゃん。捜し物はどこにあるか見当ついているのかしら」
「あ、うん。またお店に出していない子だったと思うから、たぶん倉庫にいると思うんだー」
少女はさながらバーのような対面式のカウンターを、ぐるりと回るようにして奥へと入る。
残る二人はそのままテーブルを這うように等間隔に並んでいる椅子へと腰掛ける。
全て木で出来たカウンターはアンティーク然として室内に深みを与え、且つ中の天地と色合いを合わせてとても落ち着いて見える。
「二人はいつものでいいかな?」
壁に打ち掛けられた明るい灰茶色のエプロンを首からかぶる少女は、
「うん。お願いー」
「えぇ、ありがとう」
二人の返事に笑顔を浮かべ、カウンターの内側に整然と置かれている調理器具から薬缶を取り出し、水場で蛇口をひねって水を注いでいく。
満たされたそれは存外に重く、小さくかけ声と共に持ち上げてコンロへ乗せ、火をいれる。
奥へ振り返り、木棚の小さなガラス扉を開けて、白く滑らかで丸みのあるポットを取り出す。
それを後ろ手に水場近くのシンクへ置くと、そのまま横の木扉のついた棚へ手を伸ばす。
その様子を千華は両肘をついて顔を乗せ、妃は姿勢正しくまっすぐと眺めている。
「・・・今日は、これと・・・これっ」
少女は棚から透明なポットを二つ取り出すとシンクへ向き直り、既に備えてあった手の平大で深みのある乳鉢に、透明なポットからスプーンで茶葉を振り入れる。
透明なポットには白いラベルが貼ってあり、走り書きの他国語が書き殴られている。
それらのポットを仕舞った少女は乳鉢に蓋をして、片手でしゃかしゃかと振る。
「今日は何混ぜたの?」
「今日はねー、寒いから生姜にカモミールを加えてみるの」
蓋を開けた乳鉢から、先に取り出していたポットへ混ぜ合わせた茶葉を全て入れる。
すると小さく鳴き始めた薬缶の火を止め、ポットへ薬缶のお湯を静かに注いでゆく。
ある程度注いで薬缶をコンロへ戻し、カウンターの腰付近についたデジタル表示のタイマーに手をかける。
「そだ、ゆいちゃん。何か探しものするって言ってなかったっけ?」
「あーうん。倉庫確認しようと思って」
「・・・じゃあ探してきなさい。後はやっておくから」
「そう?ありがとー。それじゃちょっと探してくるね」
エプロンを脱いでフックに掛けた少女はカウンターの端へぱたぱたと移動し、更に奥へと続く扉に手をかける。
「二人とも、冷めちゃうから先飲んでてねー」
言葉を残して少女が扉の奥へと消える。
「・・・私がやるわ」
「うん、よろしくー」
妃は椅子から立ち上がり、羽織っていた淡い茶褐色のコートを脱ぐと、空いている椅子へ静かに置いてカウンター裏へと歩いてゆく。
「四つでいいわよね」
「んー三つじゃない?月理、たぶん遅いよ」
先ほど少女の居た位置までくると、木棚のガラス扉を丁寧に開け、茶葉を燻らせるポットと同じ質感のカップを四つ取り出す。
「拗ねても困るでしょ?・・・それに、今日は早い気がするわ」
「ふーん・・・」
興味なさそうな千華はポケットから手の平に収まる薄い書籍を取り出すと、開いて眺め始める。
「・・・それ、なに?」
「酒米の図鑑。結構種類あるんだよー」
「・・・そう」
一時の静寂。
静かにページを捲る紙ずれの音と、少し遠く、カウンターの端からがたがたと小さく響く音。
切り取られた絵は朝の喧噪を離れ、短い永遠をもたらす。
と、電子音が鳴り響く。
「・・・・・・」
無言でタイマーに触れて音を止め、白いポットに手を掛ける。
溢れ出る透いた金色は、優しい立ち煙をあげてカップの中を踊る。
都合四つ。
注ぎ傾けたポットを厚手の小さなクロスに乗せた妃は、
「・・・お砂糖は?」
流麗な動作で千華の前、カウンターにカップを乗せる。
「・・・ありがと。私は蜂蜜がいいかな」
書籍を捲る手は止めずに呟く千華に、
「そうね、私もそうするわ」
言って、カウンターの真上を通ってぶら下がる、連なった同色の上棚に手を伸ばす。
すると、がちゃりと音を立てて、カウンター端の扉が開く。
「へっへー。あったよ、お目当てのものー」
嬉しそうに抱えた何かは力なくはみ出て、歩くに合わせて柳のようにゆらゆらと揺れている。
「・・・それ?」
「うん、そう!・・・あ、蜂蜜?今は種類がいくつかあるよー」
少女の声を聞きながら、妃は伸ばした手で上棚から手に収まる大きさの透明な瓶を取り出す。
「あ、それはアカシア。いつも飲んでるやつだよー。妃ちゃん、横にあるのも取ってもらっていいかな?」
「えぇ、二つとも?」
「うん。そっちの大きいのは山桜なのー。お花の香りがふわぁーってして素敵だよ」
両手でカウンターに下ろした大瓶は妃の手に余る程で、淡いピンク色の飴状のものが透けて見える。
そして妃が残る最後を取り出して上棚を閉め、コトリと手ですっぽり入るような小瓶を置く。
「あ、それでね?これはえごっていうの」
「えご?聞いたこと無いわね」
「エゴノキ、っていうのから採れるんだよー。なんかね、もってりまってりで、クセはあるかもー」
「・・・どれにしようかしら」
「わたしもどうしよう・・・」
妃と少女。
二人が悩み始めるとすぐに、
「私はエゴねー」
妃が手をかけている小瓶を掬うように手元へ持ってくると、蓋を開けて躊躇い無くスプーンを突っ込む。
そして滑らかな手つきで掬い取ると、カウンター上のカップにそっと浸ける。
「・・・私はいつものでいいわ」
カウンター裏で少女と並んでいた妃は、手に持ったスプーンで透明な瓶から蜜を掬いだし、手元のカップへ浸ける。
「それじゃ、わたしは山桜にしよっと」
少女は大瓶に手をかけ、妃は蜜を浸けたカップをカウンターに乗せる。
二人と同じように蜜のスプーンを浸けた少女は、
「二人とも、朝ご飯は?」
「食べたよー」
「食べたわ」
「そっかぁ。・・・それじゃ昨日作ったスコーンはいら・・・」
「いる!」
「いるわ」
被せるように即答する。
少女はにこりと笑い、
「そっか。それじゃ残りもので申し訳ないけど」
後ろを向いて木棚へ近寄り、フリルのついた白いキルトをつまみ上げる。
そこには真っ白なプレートに夕暮れ色のスコーンが鎮座している。
少女はプレートを持ち上げるとカウンターの下、オーブンレンジの前まで行き、蓋を開けてそれを入れて電源を押す。
そのうちに妃はカウンター裏から元居た位置まで戻り、カウンターからカップを下ろして姿勢を正す。
少女は立ったままカップに手をかけ、妃は横を向いて先を促す。
するとその様子を見ていた千華は小さく頷いて、
「それじゃ・・・いただきます」
はもるように声を重ねた少女達は各々カップを手に取り、口元へ運んでゆく。
「・・・・・・」
カップを置き、
「うん。クセはあるけど美味しい。温まりそう」
ほっと小さく一息つく。
「えぇ、美味しいわ」
「ほんと?よかったー」
カップから上がる白煙が三本、滞留する空気に撹拌されることなく天井へと立ち上ってゆく。
暫し静寂が辺りを包み込む。
食器の重なり合う音と、オーブンの小さな地鳴り音だけが室内に響いている。
すると終了を告げる電子音が鳴り響き、
「あ、できたかな」
少女はカップを置いて、両の手にミトンをはめる。
オーブンレンジを開けて中身を確認すると、
「うん、大丈夫そうだねー」
ゆっくりと取り出してシンク横の平らな面に置く。
「何個食べられそうかな?」
ミトンを外しながら話す少女に、
「私はいっこー」
「私も、一つでいいわ」
「はーい」
大きな木棚から白い小皿を三枚取り出し、カウンター備え付けの引き出しからトングを出し、一つずつ取り分けていく。
すると少女はふと視線を上げ、遠くを眺めると、再び大きな木棚に向き直り小皿を一枚追加する。
「あ、きた?」
「うん」
少ないやりとりをすると、少し遠く、入り口付近からカランと色づいた音が鳴る。
次いで等間隔に床を叩く音が小さく鳴り響いてくる。
少女は気にする様子もなく、取り分け終わったプレートをシンクへそっと置く。
そして小皿をそれぞれ千華と妃の前のカウンターに置き、更に一枚、二人の間に置く。
「ありがと・・・おいしそー!」
千華はすぐに小皿を自分の前まで下ろすと、
「いただきまーす」
スコーンに手をつける。
「じゃわたしも・・・いただきます」
少女もスコーンを持ち上げ口に頬張る。
「・・・・・・」
妃は手を伸ばさず紅茶を片手に目を瞑っている。
すると段々と大きく響いてきていた音が、妃の後ろで止まる。
「・・・・・・」
それは無言で佇む少年で、憮然とした表情を浮かべている。
「・・・食べるでしょう?」
目を閉じたまま静かに言葉を紡ぐ妃に、
「・・・まぁ食べるけど」
表情はそのまま、千華と妃の間に立ち、椅子をひく。
手に持っていた鞄とコートを背もたれに掛けると、カウンター上の小皿を一つずつ両手に持ち、ひとつを妃の前に置く。
もうひとつを自身の前に置くと、やや乱雑に椅子に座る。
「はい、おにいちゃん」
頬張る手はそのままに、もう片方の手でカップを差し出す少女。
「ん・・・」
身体を乗り出して受け取り、
「蜂蜜はどうする?」
「・・・いつもの」
少女が再度差し出す透明な瓶を受け取ると、座って瓶を開け、右手を伸ばして千華の使っていたスプーンを手に取る。
「・・・・・・」
千華は澄ました顔のままスプーンをちらと見やるが、すぐにまた食事に戻る。
少年は視線を合わせず、スプーンを瓶に突き入れていくらか掬うと、カップの中へ溶かしていく。
「・・・火傷したんだけど」
苦く、告白するように呟く。
「あら、大丈夫?」
「張本人が白々しい」
「呼び出しただけだよ、私」
「・・・ふん」
忌々しげに鼻息を荒げると、カップの中で回していたスプーンを紙ナプキンの上に置き、カップを持ち上げる。
「お前は毎回ろくな事しないな・・・」
少年はカップを傾けて口づけ、
「・・・ぐっ、ごふっ」
小さく咳こんで苦悶の表情を浮かべる。
「わぁあ!汚いよおにいちゃん!」
「・・・ちょっと月理」
「すまっ・・・ごふっごふっ!・・・なんだこれ、変な味するぞ」
カップをのぞき込んで香りを嗅ぐ少年。
「うっ、なんか変な匂いだぞ」
「えっ、生姜とカモミールを合わせただけなんだけど、そんなに変な味かなぁ」
少女は手元のカップから香りを確かめる。
「・・・特別珍しい味じゃないと思うけど。・・・カモミールだめだったかしら?」
「そんなことは無いと思うけど・・・」
妃と少年のやり取りを聞いて、
「当たり前じゃない」
「ん・・・?」
「スプーン、それ私のだもの」
千華は手元にあった小瓶を持ち上げる。
「・・・あ」
「そういうこと・・・」
妃と少女は閃き、少年は首を傾げる。
「なんだよ、また千華のいたずらか?」
「違うよおにいちゃん。千華ちゃんの使った蜂蜜、えごなんだよー」
「えご?」
「おかあさんがこの間買ってきた、ちょっとクセのある蜂蜜だよ。えごの木から採れるんだって」
「・・・それにいつものが混じったって訳ね」
妃は持っていたカップを置くと、少年の前にスライドさせる。
そして少年が口にしていたカップを手に取ると、手元に引き寄せる。
少年が顔をあげて妃の顔を見る。
「・・・交換、してあげる。駄目だったんでしょう?えご」
「・・・・・・」
代わりに置かれたカップを手に取り、口元に引き寄せる。
軽く香って、口づける。
「・・・さんきゅ」
「どういたしまして」
「はい、おにいちゃん。お口とその辺拭いて」
「はいはい」
受け取ったタオルで飛沫を拭き取っていく。
「そうだゆい。入り口の扉拭いたか?ちょっと汚れてたぞ」
「ええっ、ほんと?わー綺麗にしなきゃ」
「いいよ、ちょっとだから今やっとく」
椅子から立ち上がり、入り口の方へと歩いてゆく。
「あ、ありがとー」
遠ざかる少年に、
「頑張れよ少年」
「うっさい」
足音が遠ざかり、扉から軽やかな音色が聞こえる。
「妃ちゃん」
「・・・?なに?」
「それ・・・」
妃が手に持ち、まさに口に含もうとしているカップに視線を注ぎ、
「あれだったら捨てるよ?混ざっちゃって美味しくないと思うから・・・」
「・・・・・・」
まだ液体をなみなみと湛えるカップをじっと見つめ、
「お、いった」
くいっと傾けて戻す。
「だ、大丈夫?」
「・・・いいわ、そんなに悪くない」
言いながら再度口を付ける。
「そうだよ。そんなに悪くないよ、えご」
「おにいちゃんの口に合わなかっただけかなぁ」
「月理は保守的すぎるんだよ」
「・・・うさぎね」
「そっかぁ、うさぎかぁ」
「何がうさぎだって?」
いつの間にか少年が戻ってきていて、
「ゆい、これ洗っておいて」
「はーい」
幾分よれたタオルを手渡すと、千華と妃の間の席へ再び座る。
一息落とすとカップを手に取り、ゆっくりと口元へ寄せる。
「ふぅ・・・で、何がうさぎだって?」
「ののちゃん可愛いねーって話してたんだよ」
「な訳あるか。何か悪口に聞こえたぞ」
少女の言い訳を訝る少年。
「・・・あら、ののちゃん可愛くないの?」
「ぐっ・・・誰もそんなことは言ってないだろ」
「じゃあ可愛い?」
「や、だから論点が・・・」
「可愛い?」
繰り返し畳みかけるように言葉を紡ぐ妃に、
「・・・まぁ、そりゃあ・・・」
折れる少年。
「・・・じゃあいいじゃない」
正面を向き、カップを口元へ引き寄せる。
「うーん・・・」
納得いかない表情で同じくカップを持つ少年。
「あ、おにいちゃん」
「ん?」
そのままカップを傾ける少年に、
「ほら、これ」
両手に持ったそれは少女を二周り小さくした程度の大きさでビニールをすっぽり被り、だらりと垂れた四肢が物悲しく揺れている。
「なんだそれ」
「倉庫から見つけてきたの。ほら、昨日テレビでやってたでしょ、うさぎグッズの特集。あれに出てやつだよー」
「ふーん」
「感動少ないよー。ほら、見てみて。一番大きいやつなんだよ、これ。しかも人気って言われてた色!」
「わかったわかった。・・・で、店に出すのか?」
「出すよー。今日がこの子のデビュー日!」
「じゃあ写真は?」
「あ、撮ってほしいー」
「じゃ帰ったらな。母さんに聞いたのか?」
「この子、わたしが仕入れた子だから大丈夫。お母さんはもっと小さくて色んな色の子を仕入れてたよ」
「じゃあそれも撮っちゃうか。そいつの色違いは?」
「?この子はこの子だけだよ」
「一点モノかよ・・・」
言葉を切り、カップを呷った少年は、
「そろそろ時間だな」
カウンター上にカップと小皿を置く。
「あれ、もうそんな時間?」
千華は再び読み進めていた本を捲る手を止め、顔を上げる。
「あやー。じゃあこの子しまってくるねー」
少女はパタパタとカウンター奥の部屋へ向かう。
「・・・・・・」
妃は無言でカップと小皿をカウンターに上げると、カウンター裏へ回り込んでゆく。
「あぁいいよ妃。帰ってからやるから」
少年が続いてカウンター裏に入ってゆく。
「いいわ、いつもと同じだもの。それより拭いてしまってくれる?」
「・・・わかった」
裏手に回った妃は腕を捲り上げ、陶磁器のような滑らかな素肌が露出する。
「千華、食器あげてくれ」
「はいはーい」
カウンターに上がった食器をシンクへと移動させる少年と、蛇口をひねる妃。
食器に手をかけながら、
「月理。エプロンつけて」
「ん」
打ち掛けてあったエプロンを手にとって妃の後ろに回り、首を通して紐を腰の辺りで縛る。
その間も手早く食器を洗い、シンク脇の布巾の上に置いてゆく。
少年は洗われたタオルを取り出すと、布巾に置かれた食器を手に持ち拭いてゆく。
読みかけていた本を鞄にしまった千華は、
「んー、ふっふっふー」
にやけるような笑顔を目の前の二人に向ける。
チラりと見やる二人は、
「ん?なんだよ気持ち悪い」
「・・・なによ気持ち悪い」
「ひどっ。ハモってまでひどい」
ぶすっとした顔はすぐにまた戻り、
「・・・なんだか新婚さんみたいだねぇ」
「はいはい」
「・・・・・・」
軽くいなす少年に無言で洗い続ける少女。
「流石、余裕の貫禄ねー」
「何度も言われりゃそうなるだろ」
「あら、最初はドモって赤くなってたのに?」
「覚えにございません」
蛇口の閉まる音と共に妃が小さく嘆息し、シンク下に掛かっているタオルで手を拭く。
そのまま互い違いに柔らかく積まれた食器を、少年と動きを合わせるように素早くしまっていく。
「・・・月理、ここ拭き漏れてるわ」
「え」
「やっておくから貸して。仕舞うのはよろしく」
受け取ったタオルで白い大皿を丁寧に拭いてゆく。
「・・・はい、これでおしまいよ」
食器を手渡すとタオルを持ったままカウンター表へ出る側に歩いてゆき、カウンターの境目あたりで屈み込む。
そこには銀色のタオル掛けがあり、一面のガラス窓越しに陽光が降り注いでほの暖かい光を反射している。
それにタオルを掛けると、捲り上げていたシャツを戻しながら自身の座っていた席までいってコートに手をかける。
するとカウンター奥から扉が開き、空手の少女が出てくる。
「あやー、食器洗ってくれたの?おにいちゃん」
最後の食器を大きな棚にしまっていた少年は、
「妃がね。これでおしまいだからゆいも支度しな」
「はーい。妃ちゃんありがとー」
既にコートを羽織り、マフラーを手にしていた妃は小さく頷き、
「こちらこそ、ごちそうさま。美味しかったわ」
「そだねー、美味しかったよー」
感謝の言葉を追従する千華も既に外に出る支度が出来ている。
少女はパタパタと小走りにカウンターの表へ回り、
「ほら、おにいちゃんも早く支度しよ」
「あぁ」
つられるように少年がカウンター裏から出てくる。
と、
「・・・あ、しまった」
「?どしたの、おにいちゃん?」
「ののに水あげたか記憶にない・・・ちょっと行ってくるよ」
「そっか・・・あ、おにいちゃん、ふーちゃんのお水も替えた?」
「ふわりの分か・・・それも確認してくる」
「おねがいー」
少年は早足で千華と妃の間までくると、コートと鞄を掻き抱くと踵を返して出口へと向かう。
「先行ってくれ。すぐ追いつくから」
「はいはーい」
「・・・・・・」
軽妙な返事の千華と無言で頷く妃。
すぐに扉の方から鈴の音が鳴り、陽光の跳ねるガラス越しに少年が自宅へ駆けていくのが三人から見える。
その姿を横目に、
「それじゃ私達は向かいましょうか」
千華が率先して声をあげながら、外とを隔てる扉に向かう。
「そうだねー。それじゃ学校へいこー」
いつもの風景と言わんばかりに取り立てて心配の素振りもなく、三人は乱雑に整頓された商品の間を縫って歩き、扉を開く。
「きゃー寒い」
しかし先ほどから打って変わって吹き始めた寒波は、すぐに三人の体温を奪っていく。
「コート全然役にたたないよー」
「・・・んっ」
「きゃー」
三者三様の苦悶を浮かべながらも、少年が向かった自宅からは逆方向へ歩き始める。
「・・・風がきついわ」
コートの合わせをキュッと閉じる妃に、
「逆転の発想よ!妃」
「・・・一応聞くわ・・・何かしら?」
半ば呆れ顔の妃が逆転間近の千華の話に乗る。
「ふっふーん。・・・寒いならむしろその風を通り抜けさせればいいのよ!」
言って自身のコートを開け放つ千華。
すると待ちわびたように更なる強風が近くを駆け抜ける。
「きゃーすごいよー」
翻弄される少女に、気付けば既にコートは貝のように閉じて背を丸めた千華がぴったりと寄り添っている。
「・・・千華」
「いやー無理、寒すぎだよ。これは月理の紳士力を試すしかないね」
「え・・・紳士力?」
「・・・はぁ・・・唯理ちゃん。こんな会話、丁寧に返さなくていいのよ」
「ひどっ、妃ひどっ!・・・でもでもこういうときに何か発揮してくれてこその幼なじみでしょう!」
自信ありげに反らす胸に、
「胸にスコーンついてるわよ、千華」
「へ?・・・あ」
合わせが外れた濃紺のブレザーの胸元には、スコーンの残骸がちらほら。
「うわっ、はずかしっ」
千華は電光石火の勢いで胸元を手で散らすと、
「もう、先に教えてよね妃」
ぶぅと聞こえてきそうな不機嫌顔を表す。
「・・・話す間もないまま胸をつきだすあなたが悪いでしょう」
「うっ・・・反論しづらい・・・」
「ま、まぁまぁ二人とも落ち着こうよー。おにいちゃんそろそろ来ると、、、」
少女がちらりと後方を見やり、
「あっ、おにいちゃん出てきたみたい」
次いで千華と妃が振り返ると、小走りで追いついてくる少年の姿。
「・・・あれ?月理、手ぶらじゃない?」
「・・・そうね、見事に手ぶらね」
「あにゃー、おにいちゃん・・・」
三者三様に落胆の表情を浮かべて立ち尽くしていると、少年が三人に追いつく。
「なんだみんなで立ち止まって?いくぞー」
三人の脇を抜けて前を目指す。
「・・・待ってつき、、、」
「なんだかいつもより軽やかだね、月理」
いち早く動き出し少年に並びかけた千華は、妃の声をかき消すにように喋りかける。
「ん?軽やか?別にいつも通りのつもりだけど」
「そっかー。それじゃ今日の授業もバッチリだね」
「テストの返しと体育くらいしかないだろ・・・」
「そだっけ?でも体育あるじゃん。月理体育得意でしょー。今日はなにやるの?」
「サッカー、だけど・・・」
矢継ぎ早に繰り出される会話に違和感を覚える少年。
立ち止まり振り返ると、そこには後ろで立ち止まったままの妃と少女。
すると目が合った妃が、スッと手に持った鞄を持ち上げる。
「・・・?」
それに合わせて少年も手を持ち上げ、
「!・・・あ」
両の手が空手であることに気づき、
「・・・千華、お前わざとだろ」
「わざわざ気づかせようとしたんじゃない」
「回りくどすぎだ!・・・ったく」
踵を返した少年は再び小走りで来た道を戻ってゆく。
立ち止まっていた二人の傍を通り抜ける時、
「先行ってていいからな」
「わかったー」
そこから更にスピードを上げて駆けてゆく。
「・・・それじゃ行きましょ」
「うん、そだねー」
先で待つ千華の元へ歩きだす。
歩幅を大きくするような強い空風が、道中を阻むように吹きすさんでいた。
ちいさな小説へ戻る
Topへ戻る