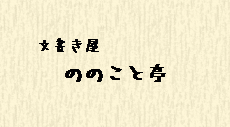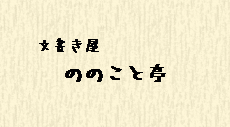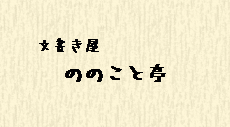 |
|
校舎は木造。
近年リフォームされたらしく木の香が未だに立ちのぼり、しかし近隣の樹齢高い森林を伐採して作られており、校内は深い年輪の中を探索しているようだ。
中庭を挟んで平行に造られた校舎と、それらを渡すように縦に繋がる建物。
その中、鞄を持って歩く姿が二つ。
自分達の教室があった校舎とは別の方へと向かっている。
「あれ、もう準備してるんだ」
渡す建物の二階。
教室を二つ連ねた程度の広がりに、クロスのかかったテーブルが等間隔に並んでいる。
「・・・サッカー部の打ち上げらしいわ」
「へぇー。確かに強かったもんね、今年」
広がりの端の方を、出口へと歩きながら眺めてみる。
奥の壁には試合の時に使われたであろう応援垂れ幕と、活躍を労う文言の踊る垂れ幕が並んで掛けられている。
「あれ?でも今日って学食休みじゃなかったっけ?」
「・・・料理部が腕をふるうらしいわ」
「じゃあ詩羽ちゃん大活躍だねー」
「・・・そうね。軽食みたいだけど」
通り過ぎる間際、ふと見えた厨房には食パンと思われる四角い物体と野菜類が堆く積まれていた。
教室のある校舎とは対になる校舎の三階。
渡し校舎から入って左奥に進んだ突き当たり。
扉に手をかけて横へ滑らせる。
一歩踏み出すと新書と古書の香りが鼻をつき、次いで鮮やかな清涼香が薫る。
すぐ左手にはカウンターが設けられて、赤白の飾り花が実るように花弁を広げている。
立ち止まり、
「何の花だろう?綺麗だね」
「・・・牡丹ね。時季的に冬牡丹じゃないかしら」
「そっかー。鮮やかながらもくどくない色味。すっきり系の薫酒に合いそうだね」
小さな嘆息と、
「・・・あなたはそればっかりね」
「なによー、駄目なのー?」
「いいえ。良いと思うわ」
足先を奥へ向け、ゆっくりと歩き出す。
その横顔は仄かに笑顔で、
「・・・まぁいいならいいけど。・・・それじゃどこ座ろっか?」
「・・・上に行きましょ」
率先して歩き出す妃に付き従うように、一歩後を追う。
等間隔に並んだ本棚。
背中合わせに本を探しても触れ合わない程度に幅が取られていて、人の姿が見えない今は悠然と歩くことが出来る。
そうして少し歩いた先、円形に吹き抜けた広がりが現れ、その中央を螺旋状の階段が聳える。
その階段に足をかけ、ふと振り返る。
「なに?」
「・・・別に」
後ろを続く千華の後ろ、誰も後続のいないことを確かめて、淡々と階段を登っていく。
ゆっくり二回転分。
登り着いた先は背の低い本棚に囲まれ、その外側には人の背丈程の鉢植えが並び、壁際には四人程で囲める机が等間隔にぐるりと配置されている。
人気は無く閑散とした様子に、
「・・・端が空いているわ」
窓際の机まで歩いてゆき、鞄を置く。
それに倣った千華は、
「何か選んでくる?」
「・・・いえいいわ。持ってるものを読みたいから」
「そう?それじゃ私もいいかなぁ」
二人で椅子を引いて座り、鞄から先程しまい込んだ書籍を取り出す。
千華はノートも取り出すと、ぴょこぴょこと飛び出した付箋を手繰りながら目当てのページを探す。
「・・・そのノート、どこで探してくるの?」
「あ、これ?これは笑乃さんが京都で仕入れてきたやつをもらったんだー」
開き止まったページは入念に書き込みがされていて、所々に簡単な挿し絵も書き込まれている。
「・・・それ和紙?」
「そうだよー。可愛くない?」
「・・・そうね、あなたらしいわ」
視線を落とし、自身の前に置いた書籍に手を掛けると、
「・・・場所はここでよかったかしら」
「ん?いいんじゃない?どうせもう少ししたら騒がしくなるんだしさ」
二人の視線は各々の手元に落ち、先の言葉の余韻が残る程の静けさが辺りを覆う。
身じろぎも無く、閉め切られたその場所は絵画のようで、時々ページを捲る腕の動きに生を気付かされる。
採光の窓は大きく晴れ上がった陽気を蓄え、外を歩く人の厚着姿を否定するように暖気を振りまいている。
微睡むような静謐に、二人は没頭する。
遠くに定刻を知らせる鈴の音が聞こえる。
ほぼ同時、引き戸が開かれるカナざり音。
聞き取れはしないがガヤガヤとした音の連なりに、
「・・・・・・」
妃が机に置いていた栞を持ち、挟み込んで書籍を閉じる。
隣の椅子に置いていた鞄に手を入れると、中から手のひら大のポーチを取り出す。
そして軽く嘆息すると立ち上がり、
「・・・飲み物を取ってくるわ」
返答を待つ気は無いのか、すぐに席を立ち歩き出す。
千華は視線も声も上げず、ただ書籍とノートに視線を行き来させている。
窓際の机から対角の位置、本棚の途切れた角地に暖簾が掛けられている。
手を当ててくぐると小部屋になっており、シンクと給湯器が備わった水場に背の高い戸棚が三架並んでいる。
手に持ったポーチをシンクに置きつつ戸棚に身体を向ける。
戸棚は三段に扉が仕切られ、中央の戸棚の上段を開くと更に数段に間仕切られた空間にビッシリとタンブラーが並べ置かれている。
その最下段に目をやると、手前左側に並んだ二つを取り出す。
それらをシンクに置くとそれぞれを捻って口を開ける。
そしてポーチを開き、円柱状の鉄器と木器を取り出す。
鉄器は筒状になっており、先を摘んで引っ張ると開いた口から仄かに甘い香りが漂う。
残った本体側を開いたタンブラーに傾け、中に薄茶色の顆粒を振り入れる。
鉄筒をしまうと、次いで木器も同様に先を摘んで開いた口に中身を振り入れていく。
こちらは緑茶色の粉末状だ。
入れ終わると筒をポーチに仕舞い、シンクに二つある蛇口から赤い線の入った方を捻る。
垂れ落ちてくる小さな流水を眺めていると、先程遠かったざわめきが近づき、誰かがさえずっている声であるとわかる。
すると流水から湯気が立ちのぼり、妃は片手にタンブラーを持ってその流れる湯を受け止めていく。
話し声はすぐ後ろまできていて、唯一隔たっていた暖簾もその誰かによって取り除かれると、
「あれ?姫ちゃん?」
「・・・おはようございます、先輩」
蛇口を止め、タンブラーの口を閉めながら会釈をする。
「うん、おはよー。なに、姫ちゃんのトコも自習なの?」
「はい」
先輩と呼ばれた少女は左端、シンクに近い側の戸棚の前に立つと上段を開けて、立ち並ぶタンブラー群から自身のものを迷うことなく取り出す。
「うちは新舛の授業だったんだけどねー。なんか始業の前に来てバタバタ答案配ったと思ったら自習だーって」
「・・・よかったですね」
タンブラーを持ち替えて開いた口をシンクに構え、蛇口を捻る。
「うんそりゃあね。でも大学入試を目前に控えた生徒達を放置で何してるんだか・・・」
「・・・・・・」
「それが噂だとね、最近ちょー美人な人がちょくちょくうちの学校に出入りしてるみたいなんだよね。んで、男性教師達はその人目当てに空き時間なんとか作って応接室に入り浸ってるらしいよ」
声のトーンを変え、密やかに話すその内容にも妃はあまり興味を示す素振りを見せず、
「・・・そうなんですか」
「あら、冷めた反応。あまり興味なかった?」
「・・・無いといえば無いですが、自習になるのはありがたいですね」
「だよねー、それはいいよねー」
タンブラーの口を閉め、ポーチとタンブラー二つを手に持つと、
「それでは失礼します」
「あ、うん。まぁうるさくて面倒かもしれないけど、また顔だしてよ。新部長も喜ぶし、さ」
「・・・はい、是非」
会釈をして暖簾を肩で当てて出て行く。
出てすぐの机には女子が数人座っていて、
「あ、姫ちゃんだー」
「おはー」
思い思いに挨拶をしてくる。
「・・・おはようございます」
会釈をしつつ、通り過ぎて真っ直ぐと元居た席へと向かう。
席には相変わらず資料とにらめっこしている千華と、
「遅いよ妃ー。あたしのど乾いちゃった」
「先程振りですわね、妃ちゃん」
登校を一緒した天梨と詩羽が向かい合って座っていた。
「・・・・・・」
特に何も答えず席につくと、
「水くさいなー。自習ならそう言ってくれればいいのに」
座ったまま両手足を伸ばし、ぐったりと机に頬をつける。
「・・・あなた達も自習だとは思わなかったわ」
「そう?ザクトモなんて年中自習じゃん」
「・・・ザクトモ?」
「倫理の作田先生ですわ。名前が智さんだから」
「ザクトモ」
「・・・そう」
「でた、妃の『そう』。まー興味無い時に出るよねー」
「・・・・・・」
手元に置いていたタンブラーを片方、千華の前に置く。
「千華は相変わらずのめり込んだらどこまでも、だねー。妃は何やってたの?」
聞きながら妃の手元にあるタンブラーに手を伸ばす。
「・・・読書よ。ここは図書室でしょう」
伸ばされた手から逃げるようにタンブラーを移動する。
「む、なんだよー、ちょっとくらいちょうだいよ。のど乾いてるんだってー」
「・・・それなら自分の物を飲みなさい。あなたもあるでしょう」
「・・・割った」
「?・・・何をかしら」
「だから、タンブラー。割った」
手元の書籍に向けていた視線を天梨に向ける。
「・・・タンブラーって割れるのかしら」
「仕方ないじゃん割れたんだからさー。折角お気に入りだったのに」
しくしくと泣き真似をして、
「だからちょうだい!」
素早く、遠くに移動されたタンブラーに手を伸ばし、
「・・・・・・」
更に素早く動いた手によって阻まれる。
「うぐっ・・・ちぇー。いいよいいよ、適当に買ってくるからさー」
手を戻して立ち上がり、
「しーちゃんは何がいい?」
「それでしたら少し甘いものを。銘柄はあーちゃんにお任せしますわ」
「あいあーい」
てってっと軽快な動きで暖簾の掛けられた角地の方へと歩いていく。
『・・・・・・』
気付けば貸し切りだったフロアも、机では生徒達が談笑し、立ち並ぶ本棚では様々な生徒が思い思いに本を選んでいる。
図書室にしては華やいだ空気の中、三者三様の無言がその中にとけ込んでゆく。
「・・・妃ちゃんは、理系でしたっけ?」
「・・・えぇ。詩羽は文系だったかしら」
「そうですわ。わたくし理科系は苦手ですから」
「・・・そうかしら。あまり苦手なようには見えないけれど」
「ふふっ。まぁ比較すればという話ですわ。・・・それより、その先はどうするんですの?」
「・・・その先?」
「えぇ、先に進む道ですわ」
「・・・そうね。・・・まだ決まってないわ。あなたもでしょう」
「そうですわねぇ。でも、一つ決まっていることがありますわ」
「・・・何かしら」
「それは・・・」
ぱたぱたと足音が近づき、
「はいはーい、天梨っちご帰還でござるー」
両手に持ったパックジュースをドンと机に置き、椅子をひいてやや乱雑に座る。
「はい、しーちゃん。ちょい甘め」
「あら、ありがとうございます。わぁ、これ丁度飲みたかったんですのよ」
「やったね!以心伝心!んであたしはこれ」
「・・・それ飲み物だったかしら」
「いいじゃん別に。今はこれを欲していたのだよ」
と、片手にパックを持ってシャカシャカと振り始める。
「ところでさ」
振っていた手を止め、付属していたストローをおもむろに差し込み、
「二人で何話してたの?・・・ふぅー」
息を深く吐き、そしてストローに口をつけて力一杯吸い込む。
「・・・別に、いつものたわいもない話よ」
「そうですわ。いつものお勉強のお話ですわ」
「うげっ、テスト終わってんのにまだ勉強の話?あーやだやだ」
両手で耳を塞ぐ真似をして目もぎゅっと瞑る。
「・・・そうは言っても、あなた成績悪くないじゃない」
「そうですわね。あーちゃん、成績もなかなか素敵ですわ」
耳に持っていっていた両手をパックに添え、少しつまらなそうに、
「それはしょうがないじゃん」
「・・・何が」
「だってしーちゃん成績ちょーいいじゃん?次も一緒のトコ行くならあたしが頑張らないといけないし」
ふてくされたように窓側を向いて机に突っ伏し、
「あー勉強めんどくさいよー」
心底面倒そうな声をあげる。
「・・・ですって。でも詩羽はいける限り高いところに行くのよね」
するとガバッと起き上がり、
「まっじで!?じゃ無理じゃん!そうなのしーちゃん?」
と振り向いた先の詩羽は、
「・・・あーちゃん」
「あれ?涙浮かべて憐憫の表情。なにこれお別れフラグ?」
うるると涙を浮かべた詩羽は大きく頭を振り、
「違うんですの・・・わたくし嬉しくて」
「お別れがっ!?」
「・・・そんな訳ないでしょう」
タンブラーを口元に傾けながら冷静に突っ込む妃。
再び頭を振った詩羽は、
「あーちゃん・・・」
天梨を手を握り、にっこり笑うと、
「ずっと・・・一緒にいましょうね・・・」
「しーちゃん・・・」
がしっと握り返すと、
「もっちろん!墓場まで一緒だね!」
「当然ですわ。結婚から出産に至るまで一緒ですわ」
「そだね!じゃ、いっそ旦那さんもシェアだね!」
「素敵なアイデアですわ」
「・・・・・・」
妃はやや冷ややかな視線を二人に送りながらタンブラーを机に置き、
「なら身近なトコでつきりんとかどうかな!」
「それも素敵ですわ」
ガシャン!
タンブラーを横倒しにしてしまう。
即座に縦に持ち直し、水分がこぼれていないことを確認して、
「・・・失礼したわ」
二人へと視線はあげず、ぽそりと呟く。
『・・・・・・』
二人は妃を見つめた後、二人で顔を見合わせて、
「うふふ」
小さく、嬉しそうに笑う。
妃は無表情を保ったまま暖気のこもる窓際を眺めながら、
「・・・何かしら」
不機嫌を装うような口調はしかし、少し上擦った声色で、
「ぷぷっ」
堪えるように笑顔をたたえていた天梨は吹き出してしまう。
「こら、あーちゃん。めっですわよ」
「だってー」
破願したまま肘をついて顔を支え、少し前のめりになると、
「大丈夫だよ、妃」
「・・・何がかしら」
「つきりん、取ったりしないから」
合わせてこくこくと頷く詩羽。
「・・・・・・」
窓を眺めたままの妃に、
「だーいたい、月理は妃と千華にべた甘じゃない。あれじゃ誰も隙があると思ってないよー」
片手を空に突き出して、ひらひらと振る。
「・・・駄目よ」
「えっ?」
「・・・大丈夫かどうかは私が決めるもの。言われて納得するものじゃないわ」
「うーん、そっかなぁ」
「そうですわね。でも、月理君もてるから色々と気になりますわ」
のめっていた身体を戻して、腕組みしてうんうんと納得すると、
「だよねぇ。つきりん、あれで結構もてるからなぁ」
「・・・・・・」
「本人はもててる自覚あるのかなぁ」
「ないわ」
「即答!?でもチョコ結構貰ったりしてたじゃん」
「・・・あれは全て義理の認識よ」
「あらあら。中には結構凝った物もあったと思いますわ」
「・・・笑乃さんと唯理ちゃんの合作がいつもすごいから。義理でもあのレベルまでくると思っているのよ」
「あぁ、あれかぁ・・・あれすごかったよねー」
「あれはとても素敵でしたわ。唯理ちゃんには是非料理部へ入っていただきたいですわ」
「・・・帰宅部を貫くと思うけど。・・・それより詩羽。今日は料理部で何かイベントがあるのでしょう」
「あら、気付きました?」
ぽん、と手を合わせ、
「今日はサッカー部さんの打ち上げで、料理部が腕をふるうんですのよ」
「えー。しーちゃん、サッカー部のために料理作るのー」
不満げな声をあげる
「・・・何か不満があるのかしら」
「あるよ、おおありだよー。なんでウチじゃなくてサッカー部だけに作るのさっ」
腕組みをして、プンプンと音が聞こえるような不満顔を見せる。
「・・・それはサッカー部が結果を出しているからでしょう」
「うっ、・・・ふ、ふん。そんな結果主義社会なんてこっちからお断りだい」
「・・・まぁ部活なのだからある程度は楽しさを考えて活動するのが普通だと思うけれど。・・・詩羽はこの話、サッカー部から直接依頼を受けたのかしら」
二人の視線が集まると、微笑んだままゆっくりと頷き、
「そうですわ。サッカー部の新部長さんから直接お話を受けましたの。あと、顧問の先生経由でもお願いされましたわ」
「・・・そうね。それなら嫌でもやらないといけないわね」
「うふふ。別に嫌なことではありませんわ。料理部も新しい代になりましたし、折角一致団結できる機会ですもの」
「・・・これを逃す手はない訳ね」
柔らかくこくりと頷くと、
「それにあーちゃん。ラクロス部の方からも打診をいただいているんですのよ?」
「えっ、それほんと!?」
身体を乗り出す。
「ええ。新部長さんの福長さんから直々に」
「へー。・・・え、でも、あれ?ウチのトコ何か大会とか出てたっけ?」
頭にハテナを散らす天梨に、
「・・・出てないわね。何の打診かしら、詩羽」
「それはですね・・・合同のクリスマスパーティーですわ」
「・・・・・・」
微妙にひきつった笑顔を張り付けたまま、乗り出していた身体を戻す。
そして手元の紙パックを持って一啜り。
「・・・あら、嬉しくないのかしら、あなた」
「うーん・・・しーちゃんそれって・・・」
「ええ。一からの合同、という意味ですわ」
「・・・そかー」
がくっとうなだれる天梨に、
「・・・お待ちかねのパーティーじゃない。何をそんなに落ち込むことがあるのかしら」
「やー・・・うーん・・・」
煮え切らない返事の天梨を見ていた詩羽は代弁するように、
「あーちゃんは作るところも含めた一から、っていうのがお気に召さないのですわ」
幼子の戯れに向けるような微笑みを浮かべている。
「・・・なに?食べるだけ食べたいけど作るのは嫌ってことかしら」
「うん。嫌」
さくっと断言すると、片肘を立て、手元の紙パックをむにむにといじりながら、
「だってー・・・あたし料理苦手だもん。みんなよくあんな上手に作るよねー」
呆れるように羨むように呟く。
「・・・あなたチョコ作ってたじゃない、今年の始めに。月理は特に悪く言ってなかったわ」
「あぁ、あれはねー・・・」
片手を横にスライドさせて詩羽の手を柔らかく握ると、
「しーちゃんが懇切丁寧に、一から十まで手ほどきしてくれたからね!まずくなる訳ないし」
「料理は分量を間違えなければ大丈夫ですわよ、あーちゃん。一度上手くいったのですから次も頑張りましょうね」
「うぐっ、・・・うううめんどいよぅ」
「・・・なら断ればいいじゃない。一人だけ不参加ね」
「ひー、ひどいよ妃!こんな楽しそうなこと、参加せざるを得ないじゃん」
「・・・それじゃあ諦めて一緒に作ることね。大体、新しい部長に言っておけばそんなに重い担当にならないでしょう」
天梨は大きく頭を振って、
「だーめだめ。新部長のふっくーは『キツいことこそやってみろ!』って感じだもの。苦手だーなんて言おうもんなら率先して担当にされちゃうよー」
「・・・難儀なものね」
タンブラーを手に取って口元に傾ける。
「あら、でもラクロス部さんとのパーティーは妃ちゃんも参加していただくつもりですわ」
「・・・なぜかしら」
傾きを戻し、真っ直ぐ詩羽を見つめる。
「だって妃ちゃんは料理部の特別部員ですもの。わたくしとあーちゃんもおりますし、是非ご参加いただきたいですわ」
「そだね、折角だし妃も参加するといいよ!てか、ウチの部にも縁あるじゃん」
「・・・そうだったかしら」
「夏の大会。千華と一緒に出てくれたじゃん」
「あらそうでしたわ。あの時は三人とも格好良かったですわ」
「あれは良かったなー。全国大会まであと一歩だったし、ウチの部で燦然と輝く歴史だね」
「・・・私には黒歴史ね」
苦虫を潰したような表情で再び口をつける。
「そんな事言っちゃってー。妃の活躍、正直びっくりしたもん。千華と二人で写真バンバン撮られてたし」
更に嫌悪感を露わにすると、
「・・・全ての記録と記憶を消去したい気分だわ」
「あははっ、まぁ活躍税だと思うしかないっしょ。千華なんてMVP取ってるから尚更オファーが凄かったみたいだし」
三人の会話が飛び交う中でも、顔を一度も上げずに没頭する千華を見て、
「・・・この子は特別よ」
小さく呟く。
「・・・でもさ、ぐししし」
子供が企んでいるような含み笑いを浮かべる天梨は、
「知ってる?つっきーのスマホの待ち受け画像」
「あ、知ってますわ」
「・・・なにかしら」
「待ち受けの画像、千華と妃がラクロスの試合してた時のやつみたいだよ」
「・・・随分雑な嘘ね」
「うそじゃないよー。だって妃、つっきーの待ち受け画像見たことないでしょ?」
「・・・ないわ」
「つっきーのクラスの男子が見たって言ってたもん。しかも、いつもスマホ使う時あからさまに画面隠すみたいだし」
「お二人の姿を見ていたいって気持ちはとても素敵ですわ」
「・・・・・・」
「まぁ今度機会があったら覗いてみなよ。そんなに恥ずかしがらなくてもさ」
「・・・別に。恥ずかしがっていないわ」
ついと窓側に目を向ける。
会話が途切れると周囲の喧騒が遠く小さく聞こえ、緩やかな時間の流れがテーブルを覆う。
と、カタンとペンが紙に投げ出される音と共に、
「んー・・・あれ、天梨に詩羽?きてたんだ」
素っ頓狂に涼やかな声が舞う。
「お、酒乱娘のお目覚めか」
「いきなりご挨拶ね。何、自習?」
トトンと読んでいた書物を立てて揃え、
「えぇ、テストの返却だけでしたから」
「あたし達は倫理だったよー。千華んとこは?」
「化学だよ。平均点はちょい高めだったかな。倫理はどう?」
「倫理はとても高かったですわ」
「うちんトコだけで満点三人だよ?あれ、ザクトモ簡単に作りすぎたんじゃないかな」
「作田先生?そっか、高いのかぁ」
思案顔するとすぐに閉じたノートを開き、何やら書き込んでいく。
「・・・返却は今週いっぱいよ。まだ計算するには早いでしょう」
「うん・・・ま、備えあればってね。テストの合計良ければシフト増やしてもいいって言ってたし」
「えぇっ!千華、まだ仕事増やす気なの!?」
色めき立つ天梨に、
「体調が気になりますわ」
困り顔の詩羽。
「・・・冬休みの期間限定でしょう」
添える妃の言葉に、
「うん。バイト代も出るし勉強にもなるし、いいことずくめかなぁ」
指を組んで手のひらを返してうーんと伸びをして、
「あ、でもでも、クリパはやろうね」
「当然だよ!今年はいつにする?当日は終業式終わってすぐだよね?」
「そうですわね。でもその週末、あーちゃん試合でしたわよね?」
「うわっ、そうだ試合だ。・・・でも大会じゃないからその日の日中だけだし、夜なら大体オッケーかなー」
「そっかー。じゃあ終わっちゃってからも何だし、終業式の次の日にやっちゃおっか」
「あら、わたくしは賛成ですわ」
「あたしもさんせー」
「妃は?」
「・・・異議は無いわ」
パンと手を叩き、
「それじゃとりあえず決まりで!場所はいつも通り月理のおうちで、時間は・・・どうしよ?」
「それなら、キッチンをお借りして御夕飯も皆で作ったらどうでしょうか?」
「うげっ」
「いいねー」
両極端の反応にも、
「あーちゃん、わたしくが一緒に作るから大丈夫ですよ」
微笑みかける詩羽に、
「うー・・・うん。まぁしーちゃんがそう言うなら・・・」
しぶしぶといった感じで頷き賛同する天梨。
「それじゃ買い出しもあるから、夕方には月理んちに集合だね」
頷く三人。
「それでは月理君にも言っておかないといけませんわね」
「あ、それじゃ携帯で連絡しておくよー」
「・・・それに今日は月理のおうちに行くから、言っておくわ」
「んじゃ万全だね!」
示しを合わせたように四人で飲み物を口にする。
ふと視線を窓側へ向ける。
陽光は燦々と地々へ降り注ぎ、眼下に疎らに見える人影は、皆一様に上着を手に持っている。
「暖かいのかな?」
「そうみたいですね」
「あれ、でも手袋とかマフラーは外してないね」
「・・・日差しが強いだけで、気温は低いのでしょう」
そう言って手元の本を重ねていく。
「あり?妃もう戻るの?」
「・・・もうすぐ鳴るわ。次、体育でしょう」
「あ、そだった」
千華も広げていた書類を閉じて纏めていく。
「げー。あたし達も一緒じゃん」
「そうですわね」
すぐに書類を纏めた妃は立ち上がり、
「・・洗うわ。貸して」
「うん、ありがと」
千華からタンブラーを受け取ると、奥の給湯室へと歩いてゆく。
それを見計らったように、
「ねね、千華」
「ん?」
「どうする?妃の誕プレ。またクリパの時に渡すでしょ?」
「うん、そうしたいねー。でもまだ何にするか決めてないよ」
「わたくし達もですわ」
「あ、でもね、隣町に可愛い雑貨屋さんがオープンしたんだって。よかったら皆で行ってみない?」
「いいねー。いついこっか?」
「終業式の日がいいんじゃない?あたしもしーちゃんも部活無いし。千華は予定ある?」
「んー・・・仕事は時間調整すればいいから大丈夫」
「じゃ、そこで決定!あ、つきりんにも連絡しておいてね」
「うん、わかったー」
幾分早口での会話が途切れたところに、ちょうど妃が空手で帰ってくる。
「・・・終わったわ」
「ありがと。それじゃ行こっか」
かけ声に合わせて四人が席を立つ。
本棚をぐるりと囲むように配置されたテーブルは全て満席で、そこかしこから聞こえてくる嬌声と談笑の声は、通常の図書室とは思えないような華やかさに満ちている。
一方、真ん中に配置された螺旋状の階段を下ると、上階での喧騒が嘘のように静けさに包まれる。
出口へと向かう四人も会話することなく歩いてゆく。
図書室とを隔てる扉を開き、一歩踏み出す。
最後に出た詩羽が扉を閉めると、
「ふぁー。やっぱ下の階は息が詰まるねぇ」
「下の方はやたら私語に厳しいもんね、うち」
「・・・静かにしていればむしろ居心地良いくらいじゃないかしら」
天梨は大げさに嘆息すると、
「そりゃ妃はね。黙ってろ選手権でもあったら優勝しそうだしね」
「あはは、確かに妃優勝しそうだね」
「・・・嬉しくないわ」
からかうように談笑しあい、渡し校舎へと差し掛かる。
差し掛かった先は食堂らしき広い空間。
「ここでやるんだ」
「そうですわ」
「・・・何時までやるのかしら」
「そうですわね。一応、夕方までは取ってあるようですわ」
「えっ、しーちゃんそんな長くまでやるの!?」
「いえいえ、料理部は調理をしたら軽くお片づけをして退散しますわ。ちゃんとしたお片づけはサッカー部さんにお任せしますの」
「えー、サッカー部ちゃんと皿とか洗えるのかね?」
「ふふっ、そういう心配が無いようにちゃんと、お皿とコップは紙製のものを使いますわ」
「あぁ、まとめて捨てればいいだけかぁ」
コクリと頷く。
と、厨房が見える位置に差し掛かると詩羽が、
「あら、あらあら」
困った様に両手を頬に当てて立ち止まってしまう。
「ん?どしたの、しーちゃん」
「あちら、キッチンに積まれてる食材なのですけれど・・・葉物もそのまま置かれていますわ」
「ダメなの?」
「お昼にはいただくものなのでダメという事は無いのですけれど、できれば直前まで冷やしておきたいですわ」
そういうと詩羽は厨房の方へ一歩踏みだし、
「すみません、皆さん。わたくしあちらを少し整理してからまいりますので、」
言い切る前に三人とも詩羽の踏みだした方へと足を向け、
「なにいってんの詩羽。四人でやればすぐじゃん」
「そだよ!さくっとやっちゃお」
「・・・すぐ済むわ」
「皆さん・・・ありがとうございます」
四人で厨房へ入る。
堆く積まれた四角い物体と野菜はそれぞれ小山を形成していて、
「しーちゃん。しまうのは葉っぱのやつだけ?」
「そうですわね・・・サラダにするものは根菜もしまいたいのですが、優先すべきは葉物ですわ」
「・・・まずはどれだけ収納できるか見てみましょう」
食堂然とした横長の対面キッチンに、対面から隔たった厨房の奥、銀色の業務用冷蔵庫が三台鎮座している。
歩み寄って、それぞれ観音開きの上段を開く。
「あれ、こっちスカスカだよ」
「こっちはお肉がぎっしり」
「・・・こちらも空ね。もうテストも終わって、食堂も休業なのかもしれないわ」
「そうですわね。・・・それでは、まずは葉物をあーちゃんの開けてくれた冷蔵庫に入れていきますわ」
各々示しを合わせたように軽く腕まくりをして、積まれた野菜の小山から葉物を取り分けていく。
「しっかしすごい量だね。サッカー部ってそんなに人数いたっけ?」
「確か三十人くらいと聞いていますわ。マネージャーさんと監督さんも合わせたら三十五人くらいでしょうか」
「うわー大所帯」
「くっ、うちはギリギリの人数しかいないのに。マネージャーまでいるなんて・・・」
悔しそうな表情をとりつつ野菜は丁寧に扱っていく天梨の横で、
「ふふっ、マネージャーかぁ」
「ん?どしたの千華」
「・・・・・・」
妃が訝る目線を千華に送るが、意に介せず、
「や、そういえば一年の時、マネージャーになってくれーってお願いにきてたっけなぁって」
「あ、知ってる!それ、妃にお願いしてきたやつじゃない?」
「そうそう。あれは伝説だなぁ」
「あら、そんなことがあったんですの?」
「あ、詩羽は知らないか」
「・・・ろくな事話してないで、手を動かしなさい」
「手は動かしてるよー。でね?あんまりしつこいから見かねて私が提案したの」
「あら、どんな提案ですの?」
「中間試験、妃より点数の一番高い部のマネージャーになる!ってね」
「まぁ!それじゃ今マネージャーしてないってことは、」
「そう。まぁ結果的には妃の点数を誰も超えられなかったんだけど、裏事情ってのがあってね」
「裏事情・・・」
「何か噂で、妃は数学系が苦手だっていうのが広まってね。それを掴んだ部の人達がこぞって数学だけ勉強しまくったっていう話で」
ふふっと笑う千華に、含み笑いの隠せない天梨。
妃は無表情に憮然としたまま、野菜を冷蔵庫に詰めている。
「あら、それでも妃ちゃんは大丈夫だったんですのよね?」
「うん。だって満点だもん、妃」
「まぁ!さすが妃ちゃんですわ」
「それも、全教科満点。入学一発目の中間でそんなことしたのは誰もいないって、先生の間で噂になったんだよー」
「ぷぷっ、しかもそれ、オチが酷いよね」
「そだねぇ」
「?まだ続きが?」
ハテナ顔の詩羽に、
「そう。問題はその後で、数学だけ勉強しまくった部活の人達のテスト結果、数学以外惨憺たる内容だったらしくて」
「バスケ部なんて数学以外全部赤点の子がいっぱい出て、顧問がカンカンに怒っちゃって大変だったよねー。それからしばらくはランニングしかさせてもらえてなかったみたいだし」
「まぁ、そんなことがあったんですのね」
「ま、今となっては笑い話かなぁ。妃は未だに嫌な顔するけど」
「・・・・・・」
「折角ならどっかのマネージャーやってあげれば良かったんじゃないの、妃?」
すると無表情を保っていた妃が眉をひそめ、
「・・・御免だわ。知りもしない人間のお世話なんて」
バッサリ切ると、
「・・・葉物はこれでおしまいね。まだ入るみたいだけど、根菜はどうするのかしら、詩羽」
「あらあらそうですわね」
人差し指を頬に差し当てて、
「それでは蕪と大根だけ入れておきたいですわ」
「んじゃ、サクッと終わらせちゃおう」
何となく冷蔵庫から野菜の置き場まで等間隔に立っていた四人は、視線を交わしあうと、
「・・・リレーしちゃおっか」
「それだ!」
「いいですわ」
「・・・・・・」
四通りの返事を受けて、野菜の山に一番近かった詩羽が数株まとまった蕪を手に取り、妃に渡す。
それが千華、天梨と渡っていき、
「うーん、・・・まいっか」
ごろんと、冷蔵庫中段に無造作に入れる。
それを見ていた妃は、詩羽から渡されようとしている蕪を手に取らず、真っ直ぐ千華を横切って天梨の元へとたどり着く。
「ん?どったの?」
「・・・チェンジよ」
「あぁ大丈夫だよ、適当に入れていけば・・・」
「チェンジ」
言い切った口調で、天梨を軽いタッチで元々妃がいた方へ押しやる。
「もーなんだよー」
不満を口にしながら歩いていった天梨は、
「しまうのがやりたいなら初めから言えばいいのに」
「・・・・・・」
千華はぴしゃんと立ちすくむ妃を窺うように、
「妃、しまいたかったの?」
「・・・絶句してしまっただけよ。早く済ませてしまいましょう」
すぐに再開した野菜リレーは回転良く進み、わさわさとまとまって団子になっていた野菜の山も幾分小さくなった。
「このくらいで大丈夫だと思いますわ」
「おっけー。それじゃ手を洗って戻ろっか」
厨房端に備え付けられた手洗い場で手を洗うと、
「冷たっ。しーちゃん、これお湯でないの?」
「簡易的な手洗い場のようですから、水しかでないでしょうねぇ。はい、あーちゃん」
「ありがと。・・・うー冷た。千華は平気なの?」
「え、うん。うち仕事柄もあるかもしれないけど、ご飯作るとき以外は大体水だよー」
「うへぇ。そっか、千華んちは水が命だもんね。・・・妃は?水冷たくない?」
「・・・冬場の水なんてこんなものでしょう」
「いやまぁそう言われればそうなんだけどさぁ・・・」
全員が洗い終わると荷物をもって厨房の出口へと向かう。
そのまま教室のある校舎側へと歩き始めると、向かいから学生が一人、ゆっくりと歩いてくる。
段ボールを抱えて顔は窺い知れないが、
「あ、月理」
「・・・・・・」
千華と妃が小走りに段ボール学生へと駆け寄っていく。
「さっすが幼なじみセンサー。どっかの民族よりも視力いいんじゃないの?」
「ふふっ、でもお二人のは月理君限定のようですわ」
駆け寄っていく二人は、周囲に目をやって人がいないことを確認すると、
「月理っ」
段ボールで見えない正面ではなく、真横について並んで歩く。
「ん、千華か・・・妃は?」
「・・・一緒よ」
「そっか」
歩く足を止め、段ボールをゆっくりと床に降ろす。
「どうしたの、それ?」
「次の体育の備品だって。アラセーに押しつけられた」
段ボールの上部は梱包されておらず、月理がその口を開くと、
「サッカーボール?」
「ハンドボールだよ。少し小さいだろ」
「・・・なぜわざわざ月理に持たせたのかしら。備品庫にあるものよね」
「空気がぺっこぺこだったんだよ。それで空気入れておけって、わざわざ持ってきやがった」
「今まだ前の授業中だよ?」
「うちは国語だよ。ユビラキとアラセーが結託したんだろ。答案返してる最中に乱入してきたよ・・・あれ、天梨と詩羽も一緒か」
顔をあげて、向かいから近づいてくる天梨と詩羽を見つけ、
「自習だったのか?」
「うん。うちは化学で天梨んとこは倫理。さっきまで図書室にいたんだー」
「・・・月理、国語は?」
「ん、まぁまぁだよ」
「・・・それじゃわからないわ。点数は?」
両手で指を折り、
「な感じ」
「・・・そう」
「へぇ!いい感じだね」
そこに天梨と詩羽が合流し、
「やぁつっきー。何がいい感じ?」
「こんにちは、月理君」
月理はコクリと頷くと、
「あぁ、国語の点数の話だよ」
「げー、ここにも点数魔人がいるよー」
「あらぁ、よろしかったんですの?」
「・・・なかなかよ」
「そうですか。それはよかったですわ」
「先生してくれた妃に感謝しないとね、月理」
「ん・・・わかってる」
再び屈み込んで段ボールに手を掛け、立ち上がる。
「お礼はまたどこかでするよ」
「・・・別に。見返り欲しさに教えたんじゃないわ」
「そうは言っても全教科でしょ?妃、ここんトコ月理んちに入り浸ってたもんねー」
含み笑いをする千華に、
「お前だって仕事無いときは大体居たじゃないか。しかも殆どののと遊んでるだけだし・・・」
「いいじゃん。ののちゃん、かぁわいいんだもん」
「別にいいけど。おやつあげすぎないようにしてくれよ」
「はいはい。あ、それ持ってくんでしょ。ハンドボールって室内?」
「そうみたいだな。体育館集合って言われたし」
そうして一歩踏み出すと、
「じゃ。俺は着替えてるからこのままいくけど、お前等は着替えに戻るんだろ」
「そだった。そのために早めに出たんだったー」
「んじゃな」
「はいはーい」
四人の声を背に歩き出す。
四つの視線は背中を捕らえたまま、やがて突き当たりを曲がって姿が見えなくなると、
「・・・いきましょ」
ゆっくりと教室へ向かい始める。
途中壁掛けられた時計の針は、終業の区切りを伝える手前でもどかしげに秒針を待っていた。
ちいさな小説へ戻る
Topへ戻る