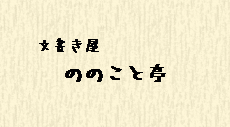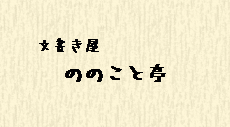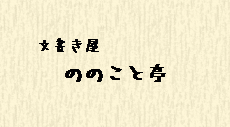 |
|
寒混じる空気の中、いよいよと重い腰を上げた太陽が空高く登り始める。
閉じられた空間。
樹木を渋めた色合いの教室は陽光を膨らませて存外に明るく、全て窓の閉じた閉塞感も特に無いようだ。
むしろ、
「・・・・・・」
眠りを促すような蜜蝋が溶け込んでいるような、その密風に中てられた生徒達が現夢の狭間を行き交う姿が多々見られる。
教壇。
壇上に人影は無く、壁全面に打ち付けられた黒板には自らで学習する時間である旨の文言が示されている。
それぞれが夢中で自己研鑽に勤しんでいる中、同じく突っ伏した格好の女生徒が、
「うーん」
悩ましげに声をあげ、
「・・・何かしら」
その横で読書する女生徒に、窘められるように言葉を返される。
「いやー、倫理も微妙な感じだったなぁって・・・」
「・・・そうかしら」
「そうなんだよー」
手元で半分に畳まれた上質紙を開き、
「このままじゃシフト増やしてもらえないなぁ、きっと」
嘆息して折り畳み、枕にする。
「・・・お父さん、そんなに厳しかったかしら」
視線は書籍に据えたまま、ポツリと呟く。
「お父さんは大丈夫なんだよー、大体オッケーしてくれるから。問題はお姉ちゃんだよ・・・」
突っ伏したまま器用に頭を抱え、
「あー、ここから挽回しないと」
「・・・お姉さん、ここの卒業生じゃなかったかしら」
「うん、そだよー。・・・まぁ主席だけどね」
むくりと顔を持ち上げ、割と遠くを見つめる。
「・・・それをあなたにも求める、と?」
「うーん、そうじゃないんだけど・・・うーん、何て言うんだろ」
上半身も起こすと片肘を立てて顔を乗せる。
「お姉ちゃんて厳しく見える?」
「・・・それは無いわね。むしろ無制限に優しいイメージがあるんじゃないかしら」
「だよねー」
そして沈黙。
書籍に手を掛け、ぱたんと閉じる。
視線を横に向け、
「・・・身内に厳しく、他人に甘い人なんでしょ」
「・・・まぁ、そうかもね」
と、とてててと効果音がするように千華達と同じ制服を纏った少女が軽やかな足取りでやってくる。
「お、みねちゃん。どしたどした?」
「うん。千華、さっき職員室に行った?」
「ん?行ってないよー。どしたの?」
「なんか職員室の方から、朝たまにする千華のにおいがしたんだ」
「朝の私?」
「うん。何だか酔っぱらいそうなふかふかしたにおいだった」
「へー、なんだろ?」
二人して首を捻っていると、
「・・・千華が朝仕事してきた時のことでしょう。お酒の香りよ」
「おぉっ。そっか。千華はお酒屋さんの子だったね」
「うん。じゃあきっとその香りだねー」
「・・・でも職員室からお酒の香りって、いいのかしら?」
「む、確かに。いいのかねぇ」
「あと、先生達が集まって喋ってる声と、なんだか女の人の綺麗な声が聞こえたんだ」
「ふむ。ますますなんだろう・・・」
「それ、知ってるよー」
千華の席の前、椅子の背もたれに手をやり振り向いた女生徒が、
「なんかね、売り込みにきている人がいるみたいで。しかもとっても綺麗な人なんだって。それで男の先生達がみんな群がってるらしいよ」
「ほー」
『・・・・・・』
感嘆する少女と、顔を見合わせる千華と妃。
「?どしたの千華ちゃん?」
「ううん、何でもないよ」
手をひらひらさせて、少々汗マーク。
「何の売り込みにきてるんだ?」
「うーん、そこまではわからないかなぁ・・・購買とか?」
「おぉ購買!だったらチーカマをぜひ加えて欲しいんだ!」
「あはは。流石にチーカマは無いんじゃないかなぁ」
「うーん・・・お、誰かきた」
少女が振り向いた先は、まだ閉じたままの扉。
するとすぐ、微睡んだ静寂にありながら音を立てずに滑り開く扉。
「おぉ、流石ねこ少女みねちゃん」
「えっへん。・・・あ、みつ穂だ!」
跳ねるように机の間を縫って駆けていく。
開いた扉からは気弱そうな少女が不安そうに中を覗き込み、既に駆けよってきている少女の顔を見て嬉しそうに安堵の表情を浮かべる。
そして出会った二人は話しながら廊下へと消えていった。
それを見送っていた三人は、
「長町さん、すごい頭良いんだよねー」
「そぅそぅ。しかもみつ穂ちゃん、ゲームもとっても上手なんだよー」
「・・・お菓子作りもなかなかよ」
「あれ?妃、みつ穂ちゃんのこと知ってたっけ?」
「・・・少し」
「そっかー」
そこで、振り向いていた少女が手をひらつかせ、
「んじゃ私はもちょっと寝るねー」
「あ、うん、おやすみー」
前に向き直って机に突っ伏してしまう。
再び訪れる静寂。
「・・・千華」
「なにー?」
「・・・職員室に来てる人って」
「うん・・・多分お姉ちゃんだよ」
「・・・学生に売り込むようなものを作っていたかしら、あなたのお宅」
「いや、ないと思うけど・・・うち、酒蔵だし」
首を捻っている千華に、
「・・・そうね」
「ん?」
「・・・これはどうでもいい情報だけど」
言葉を区切り、ずっと送っていた書籍への目線を千華に移し、身体を乗り出して近づく、
「?なに、どうでもいいのに内緒情報なの?」
言いつつ同じく身体を寄せていく千華。
そうして息のかかる距離までくると、
「・・・お姉さん、春先生と付き合っているそうよ」
「・・・・・・」
合わせていた視線を逸らし、
「・・・知ってる」
「・・・えぇ、知ってることは知ってるわ」
つまらなそうに、興味の無いような素振りで視線を再び戻し、
「あれ、妃に言ったことあったっけ?」
「・・・いえ、ないわ。ただ見かけただけよ」
「二人を?」
「・・・そうね、・・・千華は反対?」
「別にー。反対とかは特にないかなー」
「・・・の割には微妙そうね」
「・・・・・・」
定まらない視線は中空をふらふらとさまよい、
「だって・・・」
膨らした頬はほんのりと紅く、緩く潤ませた瞳に妃は小さく息を飲み、
「・・・だって?」
「・・・春先生、下戸なんだもん」
「・・・・・・」
瞬間、少し間をおいて、張りつめた空気に針を刺すようにぷしゅると頬袋を萎ませる千華に、
「・・・今月のワーストアンサーね」
肩を落として大きく嘆息する妃。
「ワースト!?こっちは大問題だよ!」
ギャン返すツッコミにはもう目も向けず、寄せていた身体も元へ戻す。
「だって、酒蔵の娘の婿が下戸だよ!?あり得ないでしょ!」
「・・・体質でしょう。仕方ないわ」
「むー。だってだってー」
机上で両手を小さくジタバタさせて、
「呑めたら色々試してもらいたいじゃん?」
「・・・それは造ってる人が言う言葉じゃないかしら」
「むっ。妃きついー」
「・・・当たり前の話よ。・・・それよりあなた」
普段の淡々とした態度とは裏腹に、大きく丸い瞳には星が瞬く程に輝いていて、
「・・・近しい人には須くそういうものを求めるのかしら」
その瞳を細めて影をつけ、そう思いこむ者には蔑むように見える視線で千華を貫く。
「うっ」
心を当てられたように呻くと、
「・・・そんなんじゃないけど・・・」
言い訳も真っ直ぐ返せず、小声で呟くと、
「・・・それなら、私が呑めないようなら付き合いを考えるっていうのかしら」
「そうじゃない!」
机を叩く勢いで腕を振り置き、風が巻き起こるような速さで妃に振り返る。
「・・・そう。それならよかったわ」
頷くように首を傾げて目を閉じ、読み進めていた書籍をパタリと閉じる。
「・・・妃、いじわる」
「・・・あなたが仕様もないことを言うからよ」
「話し振ったのは妃じゃん」
「でも、そういう思いでいられたら困るって事は伝えておきたかったのよ」
「うー」
もどかしく濁らせたうなり声はすぐに止み、
「うん、そだね。何でも求めるのは違うよね」
「・・・そうね。・・・でも」
「うん?」
「・・・実際呑んでみたら、あなたが下戸ってオチもあるわね」
「えっ!?家系的にあり得ないでしょ!」
「・・・何が混じってるか何てわからないじゃない。別にいいんじゃない?下戸の杜氏っていうのも」
「語呂良く言わないで!縁起悪い!私は呑めるようになったら、呑んで呑んで呑み明かすんだから」
「・・・何にせよ、成人してからの話ね」
一息ついたように鐘の音が鳴る。
間髪入れずに教室の扉が勢い良く開き、先ほど出て行った少女が室内の自席へと戻ってゆく。
その大きな音に触発されたのか、舟を漕いだり突っ伏して寝息をたてていた生徒達が覚醒し、やがて教室全体が喧噪に巻き込まれてゆく。
「・・・・・・」
妃が席を立つ。
「あ、石南花?私も行くよー」
合わせて席を立つ。
「・・・花なら何でもいいと思ってないかしら」
呆れるように愛らしく嘆息すると、
「・・・次は英語ね」
「うん。英語はいけそうな予感がしてるよ」
「・・・逝かなければいいけれど」
「言葉だからわからないけど、不穏な漢字当ててるよね?」
言葉は軽やかに踊り、足取りは静やかに。
二人の出ていった教室は、撹拌され混ぜ返された酒瓶のように、多々細々と彩りを浮かべていた。
ちいさな小説へ戻る
Topへ戻る