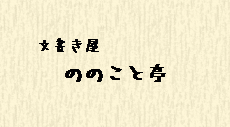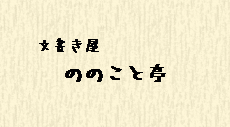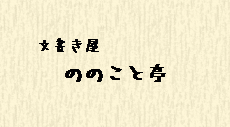 |
|
続く畦道を歩いて数分。
片端に続いていた針葉樹の壁が途絶え、コンクリート地の大きな建物が姿を現す。
道路に面する側は全てガラス張りで、その両端に出入り口らしき扉が設けられている。
通過を自動感知する扉ではないのか、千華はその扉に手をかけると身体を預けるように押し込む。
ミシミシと軋むように開いていく扉。
更に強く押し込み直角に開いたところで、妃と唯理が素早く室内に入る。
それを見届けると、千華は身体をずらして室内へ入って扉を離す。
すると扉は勢いよく戻っていき、振り子のようにバタバタと揺れている。
「おつかれさま、千華ちゃん」
「ふぅ。いつもながらこの扉は重いし怖いねー」
「・・・怪我人が出る前に直せないものかしらね」
扉を振り返りながら話しつつ、千華はすぐ近くに束なっているカートを一台引き抜く。
そこに唯理が、持ってきた買い物カゴを載せる。
そうしてカートを押しながら、
「さってと。結局、何食べようかなー」
「ねー、なに食べようか?」
「・・・ふらつけば何かあるでしょう」
「ま、そっか」
すぐに色とりどりの野菜が置かれたスペースに着く。
「やっぱ、サラダは欲しいよね」
「だよねー。あ、ルッコラとパプリカ安い」
「・・・ならそれにしましょう。イタリアンドレッシングね」
「あ、さんせー。調味料系は大丈夫かな?」
「あ、うん。オリーブオイルもあったハズだし、たぶん大丈夫だよ」
「よっし、じゃあこれで」
山積みになった鮮やかな色味のパプリカと、水の滴るルッコラをカゴに入れ、先に進む。
一段と冷えた空気が三人を包む。
壁沿いの陳列棚には冷凍の魚介類が並び、更に奥ではねじり鉢巻きの中年男性が威勢の良い声をあげている。
「・・・魚はパスでしょう?」
「うーん」
千華の押すカートの速度が下がり、様々な魚が居並ぶ陳列棚でピタリと止まる。
「・・・ちょっと、千華」
「や、ちょっと待って」
カートから手を離し、そのまま陳列された魚の乗る竹カゴに手を伸ばす。
「・・・・・・」
数歩先から振り返っていた妃は小さく嘆息すると、千華の元へと歩いてゆく。
主を失ったカートはさまようようにゆっくりと転回し始め、
「千華ちゃんがお仕事モード突入だね」
優しく宣言した唯理が持ち手を握り、カートの新たな主となる。
「・・・しばらくはかかるでしょう。私達で適当に決めましょ」
「そうだねー」
カートと共に二人は先へ進む。
ふと振り返ると、ねじり鉢巻きの男性が魚を次々と指差してゆく先を目で追いながら、何事か言葉を交わしている千華の姿があった。
カチャリ。
小瓶をカートの買い物カゴへと静かに置き入れる。
「これでいいかな?」
「・・・十分でしょ」
壁沿いにぐるりと回り歩き、カゴには食材が小さく積まれている。
押していく先には数える程のレジが並び、レジ前にはそれぞれ数人カートを引いた人々が並んでいる。
一番近場の列に並んだ二人は、
「・・・遅いわね」
「千華ちゃん?そだねぇ」
呟きつつも静かに会計の順番を待つ。
すると、一列遠くの商品棚の間から千華が顔を出す。
「いやー、いいねカサゴ!今日はこれにしよ・・・」
「しょうが焼きよ」
間髪入れずに妃がぴしゃりと言い放つ。
「あっれー?」
首を傾げてハテナマークを浮かべる千華。
「あはは・・・千華ちゃんずいぶん迷ってたねー」
「そう!そうなの!」
ずずいと身体を乗り出しつつ、カサゴらしき魚の入ったトレーを買い物カゴに入れる。
「・・・・・・」
「おじさんがね、カサゴは今が旬で、しかも今日のは特別脂がノッてるって!」
すぐ近くから刺さるような冷え冷えした視線を物ともせず、カートを握る唯理に話しかける。
「へぇー。カサゴって冬が旬なんだ?」
「そうみたい。他にもね、牡蠣は勿論なんだけど、蛤も旬なんだって!」
「そうなんだー」
会計の列が少し進み、一歩前に足を投げる。
静かに見つめていた妃は、その静けさのまま買い物カゴに手を伸ばし、
ガッ!
おもむろに手首を掴まれて停止を余儀なくされる。
「・・・ちょっと」
「買うよ。決めたもの」
二人、しばし見つめ合う。
そうして前進する力が無いのを確認したのか、千華は掴んでいた手を離し、妃も伸ばしていた手を戻して逆手でさする。
「あ、ごめん痛かった?」
すぐに心配する声色へ、
「・・・別に。・・・ただカサゴ汁がついたかしらと思って」
「ちょっと!お魚さんは汚いものじゃないよ!」
先程までトレーを持っていた手を差し出し、妃はその瞬間に半歩引いて、
「・・・わかったわ。いいから」
両手を肩の高さで小さく万歳をする。
「・・・むぅ」
頬を膨らませつつも手を戻したところで、
「お次のお客さま」
レジから女性の声がかかる。
「あ、はい」
カートを少し進め、千華が買い物カゴを持ち上げてレジ台に置く。
流れるようにレジ打ちは進み、金額を読み上げられ、レジ袋が数枚買い物カゴに置かれる。
「あ、わたしまとめておくね」
唯理がカートに掛けていたバッグから財布を取り出す。
「んじゃ後で清算だねー」
買い物カゴを持って先へ進む千華と続く妃。
すぐ先、レジと等間隔にある荷造り台にカゴを置くと、
「はい」
「・・・ん」
レジ袋を受け取り、カゴに交互に手を差し入れて品物を取りつつ、整然と袋に詰め込んでいく。
そこに、
「おまたせー」
「もう詰め終わったよー。帰ろ」
「うん。あ、わたしも持つよ」
「大丈夫だよ。あ、カート戻してもらっていいかな?」
「わかったー」
並んで建物の出入り口に向かう。
カートを戻しドアの前に立った三人に、送り出すように自動で開くドア。
そのままゆっくりと外へ出て、来た方向から逆に歩き出す。
千華はチラリと建物を振り返ると、
「出口は自動なのになぁ」
「ねー。しかも出口は外から入れないんだよね」
「・・・改善を要求するわ」
「ねー」
そこで一区切り、静寂が訪れる。
遠高に照りつける太陽は柔らかく地表を暖め、陽光が照らす田園は彼方まで茶金色に輝く。
するり、と。
一滑り、林から風が抜けてくる。
「うわっ、寒っ」
「わー、寒いね」
「・・・やっぱり冬ね」
季節を冠するような寒風は三人を撫でて田園へ抜けていき、霧散する。
畦道を歩く足音は、もう暫く続くようだった。
ちいさな小説へ戻る
Topへ戻る